「国宝松江城マラソン2022」
2022.12.10

暦の上では「大雪」を迎えて一段と冷たい風が吹くようになりました。師走も中盤になると年の瀬の準備などもあるので誰もが気忙しくなりますね。体調を崩さぬよう乗り切りたいものです。★12月4日には3年ぶりに「国宝松江城マラソン」が開催されました。新型コロナの影響もあり参加者数が心配されましたが、山陰両県をはじめ全国から2,681人の選手が集まり、城下町から宍道湖、中海の見えるコースを走り抜けました。当日の夜明け前は雨模様でしたがスタートする頃には雨も上がり、競技後半には時折青空も見える天候となっていたようです。沿道には個性豊かなボードや旗で選手を応援する姿も見られ、エイドステーションでは松江の味覚も振る舞われるなど市民全員で盛り上げるイベントになっているように感じました。ただ、これだけの大きなイベントを支える運営スタッフの方々の努力は並大抵のものではなかったと思います。市民一丸となって協力できる素晴らしい大会として定着して欲しいものですね。★最近は健康ブームということでジョギングをする方も増えているようで、私もほんの数キロですが毎日走るようにしています。フルマラソンはとても無理ですが、健康のためにも続けたいと思っています。★明日からは雲の多い不安定な天気になりそうです。タイヤも冬用のものに交換する時期になりましたね。
「成道会」
2022.11.30

早いもので今年も残すところ1ヶ月となりました。様々な出来事が起きた年でもあり余計に早く感じてしまいますね。★あと1週間ほどで「成道会」の時期を迎えます。「成道(じょうどう)」とは「悟りを開き仏道を成就する」という意味で、12月8日にお釈迦様が悟りを開かれたことから、この日は宗派を問わず全国の多くの寺院で法会が執り行われます。2500年前、お釈迦様は北インド東部の小国の王子として生まれますが、世の無常を感じ29歳の時に地位も名誉も捨て出家。その後、6年間の難行苦行を経ても真理を見いだせず、お釈迦様は苦行をやめることを決意します。そして菩提樹の下で幾日も瞑想を続け、ついに35歳の12月8日の早朝に悟りを開かれたと伝えられています。★2500年前、お釈迦様は「諸法無我」や「諸行無常」の真理を説き、同時に「人々の平等」を説いたとされています。当時、インドでは生まれによりバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王族・武士)、ヴァイシャ(庶民)、シュードラ(奴隷)などに定められる身分制度がありましたが、お釈迦様はこれを否定。最古の原始仏典とされる「スッタニパータ」には「生まれによって賤(いや)しくなるのではなく、生まれによってバラモンになるのではない。行いによって賤しくなるのであり、行いによってバラモンとなるのだ」とあります。2500年の時を経た今も考えさせられる言葉です。★週明けからは時折、強い雨の降る不安定な天気となっています。しばらくは雲の多い天候が続きそうですね。
「あいと地球と競売人」
2022.11.20
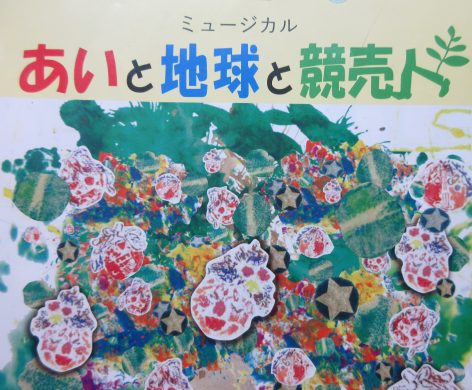
いよいよ「お忌み荒れ」の季節となりました。鹿島町にある佐太神社では11月20日から25日にかけて「神在祭」が執り行われます。神々が出雲に集うということは12世紀半ばの「奥義抄」にはすでに記されており、佐太神社の霊祭も約500年前の記録とほぼ同じ内容で厳かに進行するそうです。この祭りの時期には天候が悪くなることが多く、地元ではこの時期の悪天候を「お忌(いみ)荒れ」などと呼んでいますね。★先日、娘の後輩が出演するということでご案内をいただき、地元の有志の方々により上演されているミュージカル「あいと地球と競売人」を鑑賞してきました。これは主人公である坪田愛華さんの描いた「地球の秘密」という絵本がモチーフとなっていますが、この絵本がわずか12歳で地球環境の未来を危惧して描かれた作品であるということに驚かされます。舞台は多くの方々が愛華さんの想いを受け取り、より多くの人々に伝えたいという熱い気持ちが伝わる素晴らしいミュージカルでした。ステージ上での歌やダンス、息の合った伴奏、あるいは総合的な演出など、気の遠くなるほどの努力の積み重ねがあったのではないでしょうか。地球環境のテーマと同時に、人が夢や希望を持ち、挫けずに挑戦し続ける姿そのものに強いメッセージを感じました。★11月20(日)には斐川文化会館でも上演されるそうです。また素晴らしい公演が観られそうですね。
「炬燵開き」
2022.11.10

立冬を迎えて朝晩の冷え込みも一段と秋らしくなってきました。暖房器具のお世話になる時期の到来ですね。★いよいよ私たちもファンヒーターを出して冬の準備を始めました。自宅ではコタツを出される方も多いのではないでしょうか。江戸時代には「亥の月の亥の日」が「炬燵(こたつ)開き」の日とされていたそうです。亥(いのしし)は摩利支天(仏教の守護神・火の神)の神使とされ、火を免れる(火災が起こらない)とされてきたことから、この日が炬燵開きの日となったと伝えられています。今年の炬燵開きの日は11月6日だったそうですね。★日本で炬燵が用いられるようになったのはいつ頃からでしょうか?意外にも室町時代にはすでに炬燵があったようです。囲炉裏(いろり)の上に櫓を組んでその上に布を被せて暖を取る形が炬燵の原形のようです。江戸時代には囲炉裏を床より一段下げ、その上に櫓を組み布団を掛ける「掘(ほり)炬燵」が登場します。子供の頃、親戚の家にはまだ「掘炬燵」があり、珍しさも手伝いそのまわりで遊んだことを思い出します。現在は電気式のコタツやファンヒーターが主流となりましたが、技術の進歩した現在でもやはり火を使う以上危険とは無縁ではありませんので、取り扱いには注意が必要になりますね。★今日は終日、好天に恵まれる予報になりました。明日以降も穏やかな天気になりそうですね。
